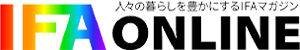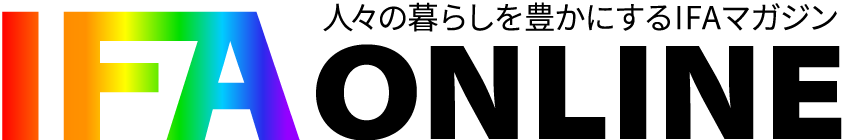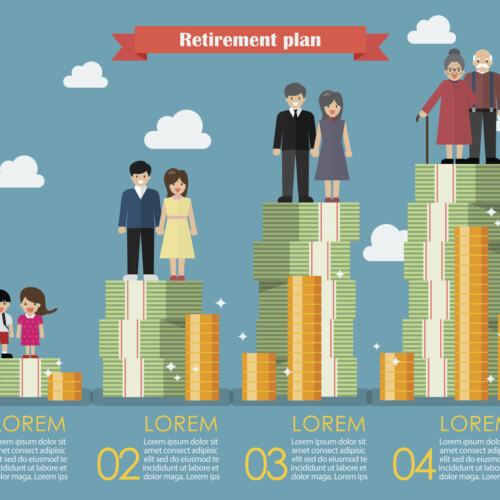投資は早く始めるほどいい? 複利の力を享受しよう

ゼロ金利政策が続く中、銀行にお金を預けても利子がつくことは、ほとんどありません。こうした状況下、預貯金以外のアクティブな資産運用が注目されています。
ところが、そうは聞いても、何から始めればいいのか、いつから始めるべきなのか、投資の初心者は戸惑うばかりです。そこで断言できるのは、「投資を始めるタイミングは早いに越したことはない」ということ。その理由を本記事でお伝えします。
「貯蓄から投資へ」は政府が推し進める重要な政策
ここ数年、メディアなどを通じて耳にするようになった「貯蓄から投資へ」というフレーズ。これは、現政権が掲げている、投資から得られる所得、資産所得を倍増させる「資産所得倍増計画」に基づいた施策です。
ご存じの方も多いと思いますが、日本の家計金融資産はおよそ2,000兆円。そのうち現預金は半分を超えている一方で、株式や投資信託に投資する人の割合は20%以下にすぎません。アメリカの約55%、イギリスの約42%に比べるとかなり低く、資産配分が預貯金に大きく偏っているのが現状です。
ところが、日本ではゼロ金利政策が継続しており、預貯金は効率的に金融資産を増やすのに向いていません。むしろ、預貯金から投資へ個人の資産をシフトさせ、それによる企業価値の向上の恩恵が個人にももたらされるサイクルを作り上げる必要があり、政府は貯蓄から投資への目標を掲げています。
具体的な取り組みとして挙がっているのは、「①NISAの抜本的拡充」「②金融教育の普及」「③顧客本位の業務運営」の3本柱です。①に関しては、ジュニアNISAが2023年で終了し、一般NISAは2024年から制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化、年間投資可能額を拡大する新制度に移行する予定で、②に関しても2022年4月からは、資産形成をふくめて高校の授業で金融教育を必修化。大学生以上に対して、金融経済教育の機会提供の推進を検討しています。③についても、金融庁は金融事業者に対して検討を求めているところです。
いずれにしても、個人の資産所得を増やすには、貯蓄から投資へと金融資産の構成をシフトさせることが有効です。そのためにも、これら3本柱の取り組みは一体的に進められ、国民の意識も変わっていくと思われます。
すでに変化は表れています。野村総合研究所が全国約1万人を対象に金融行動や意識を訪ねる「生活者一万人アンケート(金融編)2022」によると、投資経験者の割合は32%と、この10年で12ポイント増加。現在では18~79歳の47%が投資経験、あるいは投資に興味があると答えています。また、2023年3月末の証券会社のNISA口座数は1237万口座と、2022年末と比較して5.0%も増加。20歳代~40歳代といった現役世代を中心に、口座保有者が多いことが分かっています。子どもの教育費やマイホーム取得、老後資金など、何かとお金の心配がつきまとう人たちは、すでに行動を起こしています。
資産運用は早くから始めることが重要

いざ、投資の重要性がわかったとして、いつから始めるのがベストでしょうか。これに対して、「早ければ早いほど良い」というのが答えになります。なぜかというと、投資は時間を味方につけるほど効率的になり、パフォーマンスを最大化できるからです。
例えば、65歳までに想定利回り3%で運用し、2000万円をためるに必要な毎月の積立額を考えましょう。(※)
50歳から始めた場合:毎月89,000円(投資元本16,020,000円)
40歳から始めた場合:毎月45,000円(投資元本13,500,000円)
30歳から始めた場合:毎月28,000円(投資元本11,760,000円)
20歳から始めた場合:毎月18,000円(投資元本9,720,000円)
ここでわかるのは、早いタイミングで始めた方が毎月の積立金額は少なくなり、投資元本も少なるということ。20歳から始めると投資元本は目標金額の半分以下ですみます。対して、50歳から始めると毎月の積立金額は高額で、目標金額の8割を投資元本でカバーしないといけません。
次は見方を変えてみましょう。毎月の積立金額1万円を想定利回り3%で運用した場合のパフォーマンスは、投資期間によってどう変わるでしょうか。
10年間:1,400,000円(投資元本1,200,000円)
20年間:3,280,000円(投資元本24,000,00円)
30年間:5,800,000円(投資元本3,600,000円)
40年間:9,190,000円(投資元本4,800,000円)
年数が増えるほど雪だるま式に金額が増えているのがわかると思います。投資は早く始めて運用期間が長くなれば、資産をより多く増やせることがわかります。これらのシミュレーションは想定利回り3%を確保できた場合であり、実際にそうなるかどうかわかりませんが、時間を味方につけたほうが、投資の効果が高まることは理解できたと思います。
※参照:大和証券「カンタン!つみたてシミュレーション」
利益が新たな利益を生み出す「複利効果」を活用
先に挙げたシミュレーションのように、早く投資を始めたほうが少ない投資元本で目標金額に到達できるのは、「複利効果」があるからです。
複利効果とは、運用で得た収益を再び投資に回し、利益が新たな利益を生み膨らんでいく効果のこと。元本だけに利子が付く「単利」と異なり、資産を雪だるま式に増やすのに効果的です。例えば、100万円を年利5%で運用した場合を考えましょう。
単利では足し算的に資産が増えるのに対して、複利は掛け算的に増えていきます。投資期間が長ければ長いほど差が出るので、これも投資を早く始めた方が良い理由です。
投資を早く始めると「リスクの軽減」効果も期待できる

投資を早く始め長期間にわたり継続すると、複利効果だけではなく「リスクの軽減」も期待することができます。
例えば、1~2年という短期投資の場合、複利効果が得にくいばかりか、その間にリーマンショックや新型コロナウイルスのようなパンデミックが起きると、リターンが大幅に低下する可能性があります。ところが、5年、10年の長期投資になると、相場は上下しながらもリターンは安定する傾向が高くなるのです。運用期間が長いと1年あたりの運用コストを抑えることもできます。
投資先を分散させるのもポイントです。投資の世界には「卵を1つのかごに盛るな」という格言があり、これは卵をいくつかのかごに分けておくと、どれか1つを落としてもすべては割れないという、分散投資の重要性を説いたもの。投資する対象を複数にわけておくと、どれかが値下がりしても他が補完するなど、全体的なリスクを抑えることができます。一般的には日本株・外国株・日本債券(国債)・外国債券(外債)の4種類に分散して長期投資するのが、セオリーとされています。
毎月1万円など、定期的に一定の金額で金融商品を買い付けるつみたて投資も、リスクを抑えた長期投資の手法です。定期的に一定金額を積み立てると、金融商品の価格が高いときは少数を、反対に価格が安いときは多くを購入し、平均購入単価を平準化することで利益を生まれやすくします。税制優遇を受けながらつみたて投資ができる、つみたてNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すれば、より高い投資効果を見込むことも可能でしょう。長く取り組むことで、非課税扱いをはじめとする制度上のメリットを享受することが可能です。
このように、若いときから長期投資を始めると、さまざまな恩恵に預かることができます。まずは少額でも構わないので、最初の一歩を踏み出してはいかがでしょうか。悩みや不安があるなら、証券会社の営業職やIFAをお尋ねください。